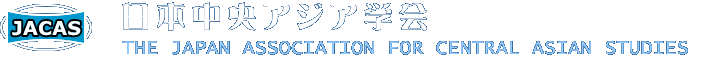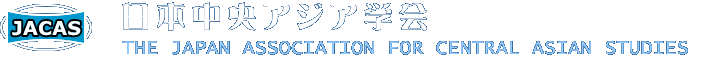2023年2月11日(土) 2023年2月11日(土)
- 日本中央アジア学会は、2022年度年次大会を2月6日掲載の要領で開催します。
―――会員以外の皆さまへ―――
年次大会のプログラムのうち、パネルセッション「現代中央アジアにおける言語をめぐる諸問題ー国家語・ロシア語・マイノリティ言語ー」は、非会員の方でも無料でオンライン上にてご聴講いただけます。準備の都合上、聴講希望の方は、3月14日(火)までにこちらに必要事項をご記入ください。なお、応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。会員の皆さまで、すでに大会参加申込を済まされた方は、こちらの申込は不要です。
大会の日が近づきましたら、お送りいただいたメールアドレス宛に、Zoom会議室へのアクセス方法とミーティングIDをお送りします。大会3日前までに連絡がない場合は、お手数ですが、大会実行委員会メールアドレスjacasworkshop[at]gmail.com ([at]を@に変更した上でご連絡ください)までご連絡ください。また事前に試験開室にご参加いただく場合がございます。もし接続に問題がある等の理由で聴講いただけなかった場合、本学会はその責任を負いかねますので、ご承知おきください。また、公開パネル以外の大会プログラムは、会員限定とさせていただきます。
また、公開パネル以外の大会プログラムは、会員限定とさせていただきますが、3月4日までに入会手続き、参加申し込みを終えられましたら、公開パネル以外にもご参加いただけます。入会手続きにつきましては、本学会ホームページ「学会の概要」の下部にあります入会規定、連絡先をご覧ください。
 2023年2月6日(月) 2023年2月6日(月)
- 日本中央アジア学会は、2022年度年次大会を以下の要領で開催します。会員の皆さまは、お送りしたメールからリンクされているGoogleフォームを使って、2月20日までに参加申込をしてください。
日程:2023年3月18日(土)~19日(日)
開催形式:ハイブリッド(オンライン+対面)
対面会場: 日本貿易振興機構アジア経済研究所
(会場までのアクセスはこちらをご参照ください)
共催: 日本貿易振興機構アジア経済研究所
プログラム(敬称略):
3月18日(土)
13:30~18:00 【個人発表①】
土居海斗(北海道大学)「中央アジアの幸福度とコミュニティーアンディジャン州におけるマハッラの調査および計量分析からー」
東田範子(東京芸術大学)「カザフ音楽の演奏慣習に関する試論ーなぜドンブラ奏者は演奏の最後に音を止めるのかー」
イブロヒモワ・ズライホ(東京外国語大学)「ウズベキスタンにおける高等教育の現状と課題についてー独立後の国家教育政策に焦点を当ててー」
加藤優弥(筑波大学)「カザフスタン核関連輸出管理法制の発展とNSGガイドライン改定の関連性 ー独立からNSG参加までの制度設計過程においてー」
3月19日(日)
9:30~11:30【個人発表②】
中村朋美(日本学術振興会)「シベリア要塞線とアジア貿易ー1830年のシベリア税関区からの報告が語るものー」
石山実弥(筑波大学)「中央アジア・ビューローによるプロパガンダの分析」
12:50~13:40【総会】
13:50~16:00【公開パネル】
「現代中央アジアにおける言語をめぐる諸問題ー国家語・ロシア語・マイノリティ言語ー」
趣旨説明:小田桐奈美(関西大学)
報告①徳永昌弘(関西大学)「中央アジアにおけるビジネス言語としてのロシア語―ウズベキスタンに焦点を当てて―」
報告②小田桐奈美(関西大学)「基幹民族によるロシア語併用ービシュケク市におけるコード・スイッチング現象を中心にー」
報告③タスタンベコワ・クアニシ(筑波大学)「中央アジア諸国の言語教育政策における母語教育権利保障の利用と濫用ーカザフスタンに焦点を当ててー」
報告④櫻間瑞希(日本学術振興会)「タタール語を選択すること、選択しないことの背景要因ータシケント、アスタナ、ドゥシャンベのタタールの事例からー」
コメント: 櫻間 瑛(独立研究者)
質疑・討論
※ 公開パネルおよび総会の開始時間を10分間前方に修正いたしました(2023年2月26日)。
※ 報告タイトルを一部変更いたしました(2023年3月7日)
 2022年10月9日(土) 2022年10月9日(土)
- 中国ムスリム研究会事務局より「中国ムスリム研究会第40回定例会」の告知が届いております。詳しくは研究会情報のページをご覧ください。
 2022年5月3日(火) 2022年5月3日(火)
- 日本中央アジア学会報17号の目次情報を公開しました。詳しくは日本中央アジア学会報のページをご覧ください。
 2022年4月9日(土) 2022年4月9日(土)
- 日本中央アジア学会報16号のコンテンツをPDFファイルで公開しました。詳しくは日本中央アジア学会報のページをご覧ください。
|