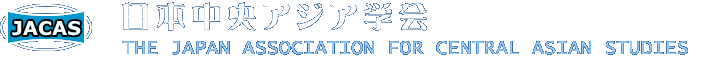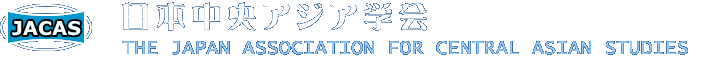日本中央アジア学会会長よりご挨拶
帯谷 知可
2024年度より日本中央アジア学会の会長を務めさせていただくこととなりました。初代会長の新免康先生は後述の「まつざきワークショップ」の時代から17年間、二代目会長の宇山智彦先生は2期8年間にわたって本会を牽引してこられました。それには及ぶべくもありませんが、お二人への感謝と尊敬の念を新たにしつつ、三代目の会長として、本会の運営に微力を尽くして参りたいと思います。
本会は、1999年に初代会長の新免先生を中心に中国領中央アジア(新疆)研究の有志により伊豆の松崎で行われた春休みの研究合宿「まつざきワークショップ」に由来します。そこに旧ソ連領中央アジア研究の有志が合流して毎年開催を重ね、これを母体に2004年3月に日本中央アジア学会が発足しました。今、自分が若かった頃を振り返ってみても、この3月の合宿形式の学会では、春休みに会員各々が小さな旅をして日本各地から集まり、中央アジア研究の最前線に触れることができると同時に、研究報告の場を離れれば高名な先生から大学院生あるいは学部生まで車座になって語り合い、とても濃密な時間を過ごした思い出があります。毎年参加するのが楽しみでした。このような経緯からも、毎年3月の年次大会は本学会の活動の柱のひとつとなっています。開催地は松崎からその後、江の島にかわり、コロナ禍を機にオンラインやハイブリッド方式が導入され、現在では会員の所属大学を会場とした持ち回り開催へと移りつつあります。
そして、もうひとつの活動の柱は、2005年から始まった学術雑誌『日本中央アジア学会報』の刊行です。論説、研究ノート、年次大会発表要旨、書評、新刊紹介、研究動向、現地事情、研究文献リストなどを掲載し、現在までに19号が刊行されています。2022年には投稿規定・執筆要領の改訂が行われ、HUSCAP(北海道大学学術成果コレクション)でのバックナンバーのオープンアクセス化が実現し、各論考にDOIも付与されることとなりました。
本学会は、規模は決して大きくありませんが、発足当初に念頭に置かれていた中央アジアだけにとどまらず、コーカサスやヴォルガ・ウラル地域、アフガニスタンなども含む中央ユーラシアや内陸アジアといったより広い地域を視野に入れ、さらに多様な学問分野にまたがる会員を有するようになりました。近年では大学院生やポスドクなど若手の方々、中央アジア出身の方々の割合も増えてきています。そのような多様性を活力として、老若男女を問わず、肩書やバックグラウンドを問わず、和やかな雰囲気の中で、自由に議論し、真摯に切磋琢磨するというまつざきワークショップの精神を継承しつつ、変貌著しい現地事情や日本の研究環境の変化などをふまえた、新しい時代の要請に応えていく必要もあるでしょう。本会が、中央アジア研究の深化や新しい研究テーマの発見につながる何かを生み出せる場であることを願ってやみません。
2021年3月の本会による「ハラスメント防止宣言」は、こうした多様性に配慮したものでもあり、この機会に学会HPでぜひご確認いただければと思います。また、子育てを経験してきた女性の会長として、研究と子育ての両立を応援するという観点から本会として何かできることはないか考えてみたいと思っております。
本会の活動は会員の皆さまに支えられて成り立っています。事務局、編集委員、監事、理事、そして毎年の年次大会実行委員をご担当いただく方々のお骨折りに感謝申し上げます。一般会員の皆さまにもぜひ本会の活動を盛り立てていただければ幸いです。皆さまからの『日本中央アジア学会報』への投稿、年次大会での発表のお申し出や公開パネルについてのご提案などもお待ちしております。
2024年4月
|